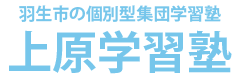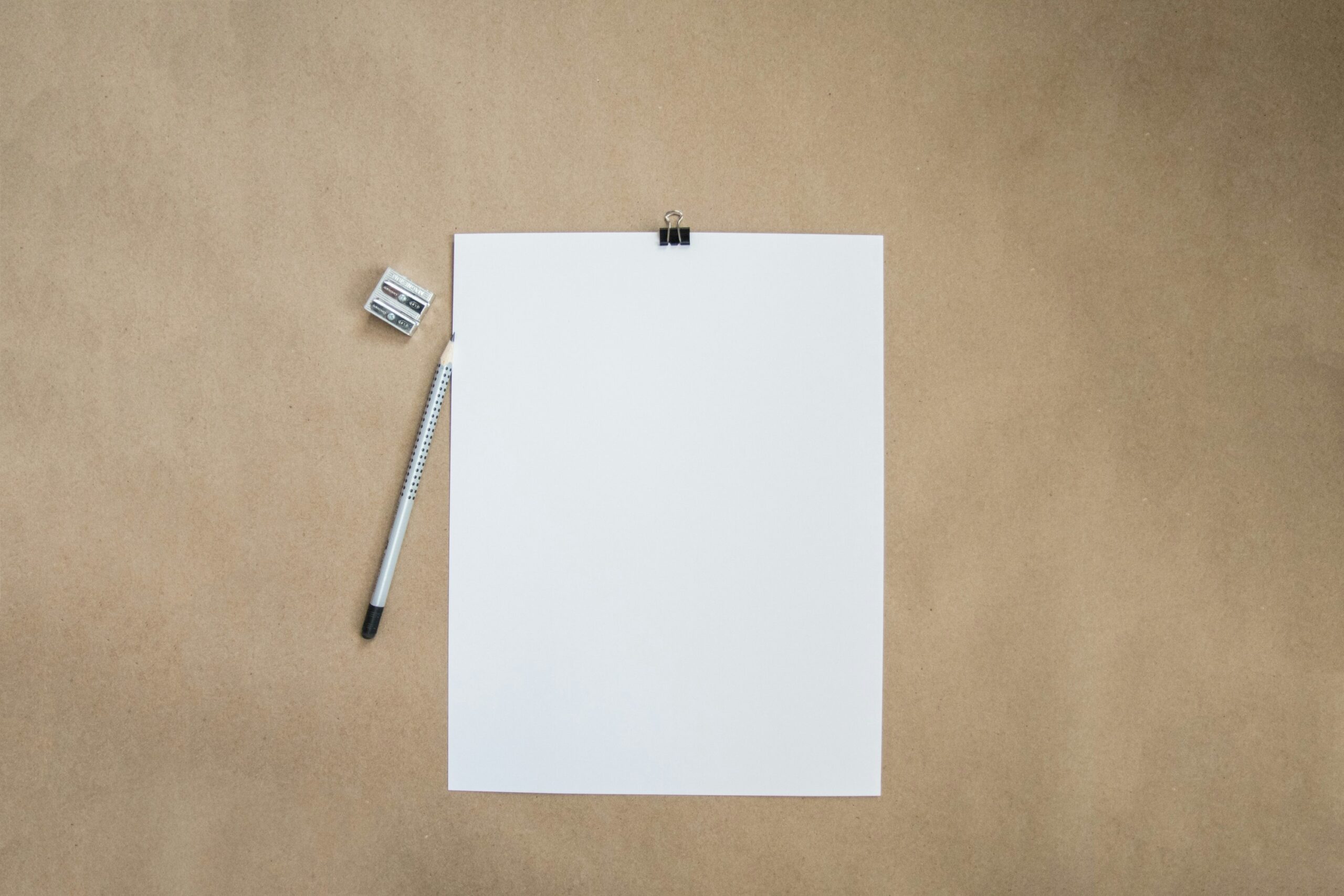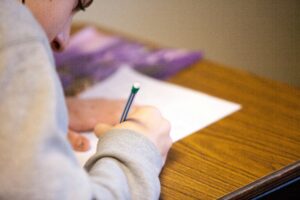こんにちは!羽生市の上原学習塾、英語大好き塾長の上原です。
今回は「北辰テストって受けた方がいいの?」と迷っている保護者の方へ。「北辰テストを受けるメリット」について分かりやすくお伝えします。
結論から入ると、塾の先生目線では北辰テストは必ず受けるべきだと考えています。
北辰テストとは?
埼玉県内の多くの中学生が受ける模擬試験です。
学校の定期テストと違い、県全体での位置がわかる偏差値や志望校の判定が示されるのが特徴です。進路選びの判断材料として、受験生にとって欠かせないデータになります。
受けるメリット
① 志望校の合格可能性・判定が「数字」で見える
学校の評定や定期テストだけでは測れない、県内での相対的な実力が明確になります。
「安全圏/合格圏/努力圏」が具体的に見えるため、志望校の調整がしやすくなります。
② 本番に近い緊張感を体験できる
他校生と同じ問題を同条件で受けるため、入試本番の予行演習になります。場慣れは本番のパフォーマンスを大きく左右します。
初めての環境でテストを受けるというのは、大きなストレスを受けます。初めのうちは自分の力を100%出すことがとても難しいでしょう。
何度もテストを受け、慣れることで本番に強くなる生徒は多いです。
③ 弱点がはっきりするから、対策が的確になる
成績表の分析で、科目別・分野別の得意/苦手が一目瞭然。
苦手単元に集中して勉強ができるので、効率の良い勉強ができます。
例えば数学であれば、結果から図形や関数が苦手であるといったことが数字で分かります。
④ 努力が成果として「見える」
点数や偏差値の変化は、子どもが積み重ねてきた学習の証です。
「前よりもできるようになった」と実感できることが、自信につながります。
塾では、自習の回数を増やした結果、数カ月で偏差値が上がり、自信をつけた生徒がいました。
この成功体験が「次も頑張ろう」という気持ちを後押しします。
⑤ 進路相談がスムーズに
北辰テストの結果があれば、「この偏差値ならこの学校が適切、滑り止めはここ、挑戦校はここ」といったアドバイスがより明確になります。
模試のデータは、塾と家庭が同じ基準で話し合うための「共通の物差し」となり、進路相談を格段にスムーズにしてくれます。
塾の先生の視点:結果があると指導の質が上がります
- 定期テストでは見えない偏差値・相対的な実力が把握できる
- 分野別データをもとに学習計画を設計できる
- 次回テストまでにやるべきこと・やらないことを明確にできる
「受けてもらえるほど、指導の精度が上がる」のが正直なところです。
よくある質問
Q. 学校の成績が良ければ、受けなくても大丈夫?
A. 定期テストは学校内の相対評価です。県内全体の位置を知るには北辰テストが有効です。
Q. 何回受けたらいいの?
A. 可能な限り継続受験が理想です。テストにも相性があります。生徒によっては得意単元が多く出たことで、いつもより偏差値が高く出ることもあります。そういった自分との相性がいいテストに出会うためにも回数を受けておきましょう。
Q. 悪い結果が出たら逆効果では?
A. むしろ弱点が早く見つかる分、有利です。次回テストまでの学習に直結させれば伸びしろになります。
Q. 悪い結果を高校に見せたくない
A. 高校の個人面談に北辰テストの結果を持っていくと、良い結果を中心に見てくれます。なので、悪い結果が出たとしても気にする必要はありません。
まとめ:迷うなら、受けておいて損はありません
- 志望校の合格可能性が明確に
- 入試本番への場慣れができる
- 弱点がわかり、勉強が効率化
- モチベーションが数字で管理できる
- 進路相談がスムーズ
最後に

北辰テストを受けるメリットについてでした。
こちらの記事が北辰テストを受けるかどうか悩んでいる方の助けになればと思います。
塾目線では、生徒の進路をしっかりと考えるうえで、模試の結果はとても大切です。
お金もかかってしまうものですが、出来るだけ回数を受けて頂けると、それだけ密な進路相談ができます。
今回の記事は以上となります。
上原学習塾では、受験のための勉強はもちろん、勉強が人生を豊かにすることを伝え指導を行っています。
塾長ブログは週に1,2回更新予定です。教育に関する記事を定期的にアップしていますので、ぜひご覧ください。
勉強の方法や進路のことはもちろん、学校生活や将来に関するご相談も承っております。
生徒の皆さんが安心して学び、未来に向かって前進できるよう、幅広くサポートしてまいります。
体験授業や学習相談も随時受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
塾長:上原明
学歴:東京理科大学 工学部 建築学科卒、埼玉栄高等学校(アメフト部)、羽生西中(陸上部)
指導歴:2007年から
趣味:映画、海外旅行、英語学習、シーズンスポーツ、ゲーム、マンガ