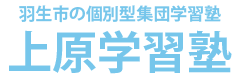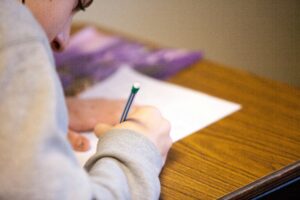こんにちは!羽生市の上原学習塾、塾長の上原です。
今回は「計算過程に力を入れることで、数学の力がぐっと伸びる」という話です。
成績が劇的に伸びる生徒もいれば、少しずつ伸びる生徒もいますが、共通して大切なのが「計算過程の書き方」です。
これは中学生に限らず、高校・大学でも求められる力なんです。
高校・大学では、「計算が正しい」よりも、「計算過程をどう書くか」に価値が置かれます。
◆「書き方」を変えるだけで、結果は変わる
塾で、計算過程の書き方を正しくするように指導した結果、学校のテスト・北辰テストが30点アップすることがよくあります。
すべての生徒に同じ変化が起きるわけではありませんが、「計算過程の書き方」を変えるだけで変わる生徒は多いです。
たとえば、以下のような式の書き方。
6+25×4 =25×4 =100 =6+100 =106
この書き方は、一見正解に見えますが「=」の使い方が間違っています。
これは、自分の中でだけ通じる「自己流ルール」になってしまっています。
また、他にも次のような例があります。
- 分数の通分を暗算し、途中式がない
- プラス・マイナスの記号が小さくて読みにくい
- 「=」が雑で「3」に見える
- 方程式の左にイコールを書いてしまう
こういった書き方のクセを直すだけで、点数は確実に変わっていきます。
◆ 高校・大学では「正解」より「過程」が見られる
高校や大学に進むと、A4の白紙に「この問題を解け」とだけ書かれた課題が頻出します。
しかも、その問題はそもそも正解が出せないほど難しいことも珍しくありません。
では、点数はどこでつくのか?それが「計算過程」です。
中学で習う証明問題のように、「どう考えたか」を書く力が求められます。
小中学生のうちから正しい書き方を身につけている生徒は、高校・大学でも困りません。
逆に「答えさえ合っていればいい」と思ってきた生徒は、ここで初めてつまずいてしまうのです。
◆ 私自身も、中学時代の指導に感謝しています
ここで少し、私自身の話をさせてください。
私は東京理科大学出身なのですが、東京理科大学はレポートが厳しく評価されることで有名でした。
数学や物理の課題では、「どう考えたのか」が明確に伝わる計算過程や論述が求められ、答えだけでは評価されません。
ですが、私はそこまで苦労せずに対応できました。
なぜかというと、中学生の頃に計算過程の書き方について厳しく指導を受けていたからです。
当時は「こんな細かいことまで…」と思ったこともありましたが、
今振り返ってみると、あのとき正しく書く習慣がついていたおかげで、高校・大学でつまずくことなくスムーズに学びを進められたと感じています。
だからこそ、私は「計算過程はただの手順ではなく、一生役立つ“伝える力”」だと思っています。
◆ 計算過程は「伝える力」のトレーニング
計算とは「自分の考えを伝える」行為でもあります。
学校でも、社会に出ても、人とやり取りする中で「自分の考えを正確に伝える力」は非常に重要です。
その第一歩が、計算過程を書くことなのです。
「自分だけが分かっていればいい」という姿勢では、成績は頭打ちになります。
「誰にでも伝わるように書こう」とする姿勢こそ、学力の伸びにつながります。
最後に

私は、計算過程を正しく書くことは、自分の考えを相手に上手く伝えることにつながると考えています。
「答えさえ合っていればいい」という姿勢は、極端に言えば“自分さえわかればいい”という考え方。
それは時に、周囲から「自分勝手」と見られてしまうことさえあります。
ある知人のプログラマーが、こんなことを言っていました。
「動けばいい、というコードを書く人と一緒に仕事をするのは正直つらい。
誰が見てもわかるような、整理されたコードを書ける人じゃないと、チームではやっていけない。」
この言葉を聞いて、私は思いました。
学生の頃から計算過程を丁寧に書く習慣がある人ほど、将来、他人に読みやすい・伝わる表現ができる人になるのではないかと。
計算とは、未来の「伝える力」の土台を作る大切な学びです。
今この瞬間から、少しずつ「伝える計算」を意識していきましょう。
今回の記事は以上となります。
上原学習塾では、受験のための勉強はもちろん、勉強が人生を豊かにすることを伝え指導を行っています。
塾長ブログは週に1,2回更新予定です。教育に関する記事を定期的にアップしていますので、ぜひご覧ください。
読んでくださった塾生、保護者の皆様は何かお困りのことがありましたら、お気軽に塾長にご連絡ください。塾をお探しの方も、どう勉強したらいいのか?などのお悩みがありましたらご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
塾長:上原明
学歴:東京理科大学 工学部 建築学科卒、埼玉栄高等学校(アメフト部)、羽生西中(陸上部)
指導歴:2007年から
趣味:映画、海外旅行、英語学習、シーズンスポーツ、ゲーム、マンガ、ボードゲーム作り